レポート|老い”から見える、ためらいと希望の哲学談義
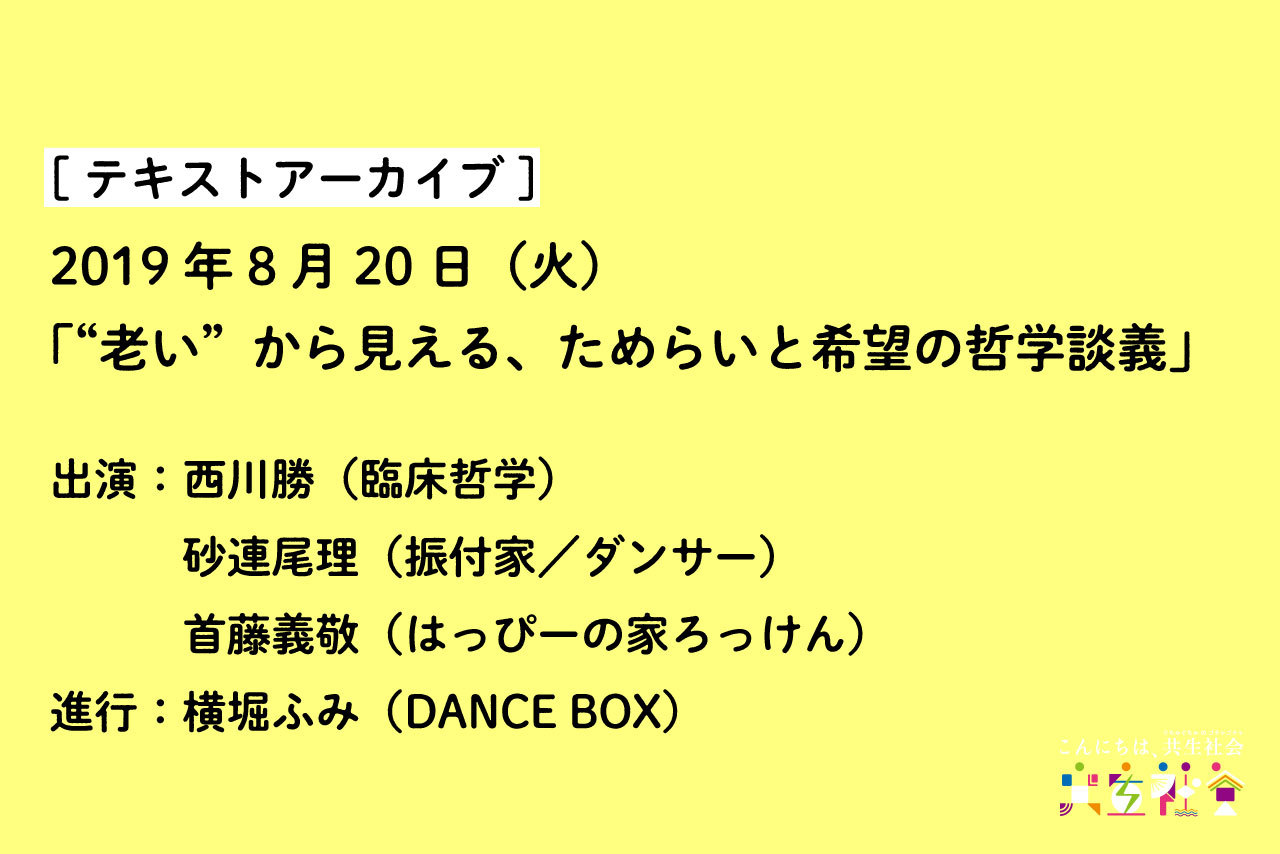
2019年8月20日
出演:西川勝(臨床哲学)
砂連尾理(振付家/ダンサー)
首藤義敬(はっぴーの家ろっけん)
進行:横堀ふみ(NPO法人DANCE BOX)

横堀 まずはじめに、それぞれの方がどういう活動をされてきたのか、事例紹介という形で進めたいきたいと思っています。その前に、今回のレクチャーに「哲学談義」というタイトルを勝手につけましたけど、はたして哲学ってどういうものなのか。この場で共有できるように、西川さん、簡単にご説明いただいてもいいでしょうか。
西川 哲学って何か。自分の経験からいえば、なかなか誰も説明してくれないから、よくわからないわけです。なんとなく立派そうとか、怪しそうとか、そういうイメージがあると思うんですけど、僕はそこに惹かれて哲学科に入ったんですね。哲学書を読むだけでインテリみたいな気がするし、大事なことを考えてるって自分でも思えるし、人からもそう思ってもらえるから、若い頃の優越感としてはちょうどよかったんです(笑)。普通、学問というのはなにかの問いがあって、一生懸命にその答えを探すわけです。ところが、哲学ってどのように問うのかって、問いそのものを考え直す。答えはどうだっていいわけです。あるいは問いがあったとしても、これって本当に大切な問いなのか。なぜこれに僕は答えなければいかないのか。この問いから本当は何を知りたいんだろう…って、問いを吟味するところからはじまるんですね。つまり、哲学というのは、多くの人が懸命に追求している問題を「ちょっと待って、それ、本当に大事なの?」ってちゃぶ台返しをするようなところからはじまるので、まあ、あまり人に好かれるようなタイプじゃない気がしますけども(笑)。今日もテーマになっている老いや死といった切実な問題について、自分たちの立場からどんな風に問うことで身を賭けてでも答えたい問いになるのか、というのをやれたらと思っています。
横堀 ありがとうございます。西川さんは最初から哲学の道に進まれたのではなく、いろんな現場を経験されて今にいたるんでしょうか。西川さんのこれまでと今の活動について簡単にお願いします。
西川 僕はね、高校に入ってその新入生歓迎の場でいきなり生徒会長に憧れまして、その人が学生運動をやってたんです。それで完全にかぶれてしまって、真っ赤なヘルメットをかぶって三里塚に行ったりしてるうちに、半年で学校にいれなくなって中退しました。これでは駄目だと思ってきっちり軟派に転向しまして、それでも大学は、関西大学の2部の哲学科を受けたんです。2部の哲学科なんて行っても就職先ないですから、みんなと競争する学歴社会に入るのはやめたってことで、だけど、自分の自尊心は守りたいという中途半端な理由で進学したんですね。で、大学に入った途端にインド哲学の先生が言うんですよ。「君たち、まさか卒業しようなんて思ってないよな」「関西大学2部は大阪でいちばん授業料の安い大学なんだから、表裏きれいにひっくり返して、図書館で本を読んだら別に卒業しなくていい。そもそも哲学に卒業なんてないから」って言われたことを真に受けてね。卒業に必要な語学の授業には出ずに、単位だけ170単位くらいとって、7年半授業料払って中退しました(笑)。その間に、もと陸軍看護婦の母親が「この子の将来が心配だ」って、母親は、敗戦後しばらくは結核患者の訪問看護みたいなことをやってたんですけど、精神病院で働くようになって、僕がまったく卒業する気配がないし、「とにかく健康保険証のある職場で働きなさい」とかって言うわけです。で、母親が精神病院の課長と話をして、面接の日が決まってました。もともと卒業する気もないし、専門的な哲学者になるつもりもないし、なれそうもないし、何でもいいやと思ったので、その精神病院の看護師になっちゃって。
横堀 私も4歳の息子がいますけど、西川さんのような息子がいたらほんまに心配で。お母さんが面接の日取りを決めたって気持ちがようわかります。
西川 面接に行ってもあかんって言われると思ってました。あの頃は、学生運動やってやめたなんて言うとまず仕事はなかったんですけど、さすが精神病院の百戦錬磨の課長ですから、「ゾウリ持ってるか」「はい」「じゃあ、それ持っておいでな」って言われて決定ですよ。それで閉鎖病棟に入れられて。これが僕の最初の看護との出会いです。
横堀 いまはどういう活動をされてるんでしょうか。
西川 いまは3年ぶりに勤めるようになりまして、大阪市認知症の人の社会活動センター「ゆっくりの部屋」に。センターといっても従業員1名ですけど、そこの責任者をやってます。7月31日に開所したばかりですから、まだ1か月も働いてない。
横堀 おいおいまた聞かせてください。では、砂連尾さんと首藤さんの活動紹介もお願いしたいと思います。はじめに砂連尾さん。ダンスボックスとのつきあいはもう長くて、20年以上ですかね。
砂連尾 ダンスボックスができたときから。設立メンバーの文さんとは、ダンスボックスができた96年より前からですから、四半世紀近いつきあいだと思います。
横堀 砂連尾さんとは「循環プロジェクト」という事業でご一緒させてもらったことが、ダンスボックスの活動にとっても大きな転機になりました。「循環プロジェクト」は、障がいのある人と一緒に舞台作品をつくるというプロジェクトですけど、今日は、砂連尾さんが高齢者の方といっしょに舞台をつくられて、現在も続いてるその活動についてご説明いただけたらと思います。
砂連尾 みなさんは、ダンスにどんなイメージを持ってますか。ダンス=舞台のダンスを連想して、舞台のダンスといえば、ある種、特権的な身体とまでいうと言いすぎかもしれませんけど、ちょっと特別な身体である人がやるものだというイメージを持たれる方が多いかもしれません。じゃあ、僕自身がそういう身体になりたかったかといえば、決してそうではなくて、踊るのが好きだからっていうのでもなく、むしろ、踊ることは苦手で、やりたくないことの上から二番目くらいにあったもの、それが僕にとってのダンスでした。先ほどの西川さんが高校に入って学生運動に関わって、というのとは違って、僕の若い頃は高度経済成長期で、できるだけ高いレベルの学校に入って、企業に就職するという幸せの道筋みたいなのがありました。そういうことからいかに抵抗して生きていけるかって、スポーツに取り組んだりとかしてましたけど、なかなか新しい世界に出会えなくて、大学に入って、もう自分の頭で選択するのではなかなか希望が持てないなと思ったときに、自分がいちばん選択しなさそうなものを選ぼうと考えて、選んだのがダンスでした。なので、かっこよく踊ろうとか、かっこよく見られたいというのではなく、自分にとって未知なる何か、今までの日常とは違う世界が見えるのかなと思って、ダンスをはじめました。それが19くらいで、40歳くらいまで約20年は続けていたんですが、舞台芸術という世界では、単純な話、毎年、新作をつくらなければ劇場から声はかからないし、助成金ももらえないわけです。自分で否定して、競争社会には身を置かないで生きていたいと思っていたのに、そこから逃れた先で、たぶん試験でいい点をとるよりもちょっと過酷な生活が待っていたわけです。そして41歳のとき、10何年前ですけど、ダンスボックスの人たちから障がい者とのプロジェクトを紹介してもらって、それが自分にとって大きな活動の転機になりました。それまでは毎日、バーレッスンをやったりしながら、身体を鍛えていくことばかり目指してたんですけど、そのプロジェクトでは車椅子や義足の人、コミュニケーションが少しむずかしい人たちといっしょに練習をして、ともに時間をすごすわけです。そうやって車椅子の人と一緒に歩いていると、車椅子の高さでの視線が発見できたというか、そんなの当たり前だって言われるかもしれないけど、僕にとっては世界がすごく変わったんですね。義足の人と駅で待ち合わせてダンスボックスまで向かうと、普段は5分程度の道のりが15分、20分くらいかかる。それだけの時間をかけて歩いてみると、木の枝の揺れ、雲の流れ、風というものがこんなに違うんだって感じました。僕はそれまで、西洋ダンスの基準に向かって一生懸命に訓練して、身体を精緻させていってたけど、そうじゃないところにダンスがあるんじゃないかと気づいたキッカケが、その「循環プロジェクト」でした。その後、ベルリンで1年暮らす予定になってたので、そこでドイツのカンパニー、Thikwa(ティクバ)と一緒にやって、その後に帰国して、次はどういうダンスをやろうかなって考えたときに思い出したのが、僕の友人の野村誠という音楽家のことで。彼がその10年ほど前に、横浜の老人ホームへ音楽活動をしに行ってたことを知って、じゃあ、ダンサーが老人と踊るということに対して、ダンスでどんな応答があるか。まったく事例がないわけじゃなかったけど、あまり応答している事例がなかったので、僕自身が老人の方と、それもコミュニケーションのむずかしい認知症の方とのダンスが存在しえるのかって考えました。だから、最初はケアの視点というよりは、純粋に身体の可能性を探りたいということではじめたのが、老人とのダンスでした。その活動は2009年11月に「グレイスヴィルまいづる」という特別養護老人ホームに私が招かれて、3月まではほぼ週1回、それ以降も月1回通いながら、ワークショップという形で続けています。その活動については、映像で見ていただけたらと思いますので、ちょっと見てください。
(「とつとつダンス」映像流れる)
砂連尾 この映像は、2014年につくった「とつとつダンス」という作品の続編なんですけど、ちょっと、なんというかな、あまりドラマチックな言い方をしたいとは思わないですけど、認知症の方と踊ったときに、僕はほんとに奇跡的な瞬間に何度も出会うんですね。単純に対話がむずかしいので、どうしたらいいだろうって、特に家族の方の思いはあると思うんですけど、僕はほんとに救われました。毎回、新鮮に僕に触れてもらえるというのかな。毎月、今日はどういう風に僕はこの人と出会い直せるかということを感じさせられるような存在の仕方をしていました。「とつとつダンスpart2.」でご一緒したミユキさんという方、彼女は身体が弱く生まれて、なんとかしようと思って飲んだ薬が薬害で、という人生で左手しか動かなくて。彼女は、自分の動かない右手を左手で懸命に支えて、その動かそうとしている右手に触れたときに、僕自身が触れるということを学ばせてもらっていると感じるような瞬間が何度もありました。最初は、どういう風にダンスが可能かというので出会った人たちから、どう人と関わるか、生きるか、そして触れ合うかということを、僕自身が学んでいったこの10年だったと思います。
横堀 ありがとうございます。西川さんもこの「とつとつダンス」にははじめの方から関わっておられるんでしたっけ。
西川 舞鶴であった「とつとつダンス」のアフタートークに呼ばれたんです。それまでは、まったく砂連尾さんのことを知らなくて。さっき話した精神病院で15年、その後、血液透析の現場で5年、それから臨床哲学ということばを知って、昔の哲学の火がつくんですね。で、大阪大学にモグリで行きはじめて、社会人で大学院に入って、大阪大学コミュニケーション・デザインセンターの教員にまでなります。世間からはいっぱしの認知症の専門家みたいに思われて、このアフタートークに呼ばれて行ったんですけど、まあ、びっくりしましたね。僕も看護の世界では変わった人間でしたけど、それもぶっ飛ばすような。だって、後ろから目隠ししたり、自分の着ているパーカーをかぶせたり、子どものように抱っこしている人形をとりあげたり。要するに、現場では絶対にしてはいけないとされることばかりが続くわけです。それを正しい、正しくないって見てる自分がいたんですけど、いつの間にか砂連尾さんとミユキさんのあり様、こんな美しいことが起こるんだって最後のシーンを見たときに、自分が20数年にわたって考えてきたことを根っこからひっくり返されてるなと思いました。もう一度、問いを考えなおそうと。それまでは、認知症とどう関わるべきかって、看護の視点からやったわけですけど、こんなに美しい出会い方があるじゃないかと。どうやって美しく出会うかなんて看護師は考えてないわけです。それで、次に砂連尾さんが伊丹に来たときに訪ねて「お願いしますから僕を混ぜてください」って、それからほぼ10年。ずっと追いかけています。
横堀 追いかけてみていかがですか。
西川 やっぱりだいぶ変わりました。まずケアをいちばんに考えるってことがもうないですね。
横堀 じゃあ何をいちばんに考えますか。
西川 なんでしょうね。共生ということばはあれですけど、共にいるってこと。そのことの意味をすごく考えるようになりました。僕が臨床哲学で学んだのは、決して哲学はひとりではできない、必ず相手がいるということ。それをすごく感じるようになりましたね。哲学って、いかに生きるべきなのかという自分の問題にしちゃいがちですけど、そうじゃないよね。臨床哲学は必ず相手がいるものだっていうけど、じゃあ、どういうことなのか。それを最近、僕はことばや論文じゃなくて、自分のことを臨床哲学のプレイヤーですって言って活動してますけど、そうやって後からだんだんわかってくる。まだわかりきってないので、まだまだ続くと思いますけど。
横堀 舞鶴でのワークショップはおじいさんおばあさんだけじゃなくて、職員の方も一緒にされてるんですね。
砂連尾 常日頃から利用者の方に接するのは職員の人たちなので、僕のエッセンスが少しでも伝わればいいなくらいの気持ちでしたけど、すごく戸惑われて、嫌がった職員さんもたくさんいました。
横堀 10年という時間を経て、職員の方とおじいさんおばあさんの接し方に変化があったりとかって感じることはありますか。
砂連尾 ふたつの感情があって、ひとつは、たしかに僕のワークで変化して、思い切ってやるということに意識的になってる人たちがいるのかなと思います。ただ、日々のこなしていかなければいけないことが膨大にあって、たぶん僕のワークに関心を持つ余裕も、それを試そうという時間もないというのが現状じゃないかな。これほど理解のある施設であったとしても、なかなか難しい現実はあるんだろうと思います。
横堀 首藤さん、これまでのお話を聞かれてどうでしょう。
首藤 すごく安心しました。お二人のことを調べずに来たんですけど、自分から中退されてたり、みんながやってることの逆をやってしまえ、みたいな二人だなと思って。
横堀 では、はっぴーの家のことをご紹介ください。
首藤 はっぴーの家はこのすぐ近く、新長田の南側にある、形は一応、介護施設です。60歳以上のおじいちゃんおばあちゃんが20人ちょっと、僕と奥さん、子ども二人で同居しています。ほとんどが認知症の方です。昨日も夜中の3時くらいに認知症のおばあちゃんが部屋に入ってきて、「朝ごはん食べよう」って言うけど、外はまだ真っ暗でした。そういうカオスな生活をしています。
そもそも介護事業をやりたかったわけじゃなくて、僕ら家族や娘が安心して暮らせる場所をつくりたいと思っても、見つけられなかったんです。子育てと介護がかぶってしまって。今日、後ろで走り回ってるのはうちの娘ですけど、僕自身、彼女のような感じでした。学校行っても、先生に「もう学校来んな」って言われるくらい、落ち着きがなくて座ってられなかった。いわゆる多動です。そこに薬を強要されるのは何か違うなと思っていて。僕は今、34ですけど、なんとかやってこれた。その理由を考えたら、結局、まわりの人に助けられたんです。そういう環境はどこに、って考えだすと、今やってるはっぴーの家につながってくるんですけど…僕が説明するよりもまとまった映像がありますので、ご覧ください。
(NHKで取材されたときの映像流れる)
首藤 という生活をしております。何がしたかったのかって、結局、僕が10年ちょっと前に結婚して、子どもが生まれるとなったときに、世の中はまだ夫婦で子育てしなきゃいけない空気でした。そもそも僕はこういう人間で、中2くらいからろくに学校に行ってなくて、友達は多かったんですけど、うちの子もそうやろうなって不安がありました。そして、同時期におじいちゃんおばあちゃんが認知症になったんですね。これは同居せざるを得ないと。といっても、他に見てくれる親族はいなくて、家族関係が完全に破綻してましたから。じゃあ、これはもう家族だけで暮らすのはしんどいから、他人も入れて15人くらいのシェアハウスとして暮らせたらいいかって、きれいな意味の助け合いではなくて、依存しあう生活が生まれたんです。僕らには子どもがいて、認知症やけど子どもを見てくれるおじいちゃんおばあちゃんがいて。要は、自分らだけでがんばらなくても、依存しあってもいいんじゃないかと思いまして。うちの奥さんも普通の主婦とは違っていて、自分は1日1食でいいから、僕らにもそれでいいやろうって言ってくるようなタイプ。そういうズレた感じでも、みんなで暮せばなんとかなるんじゃないかって、間違った仮説を立ててやってきた感じです。さっき西川さんの話に、哲学は問いを立てるものだって言われて、すごく勇気をいただいたんですけど、まさに僕がやってることは正解を出してるとは思ってなくて、こんな暮らしがあってもいいじゃないかという問いを立てることを事業内容にしています。そのためにも、世の中で当たり前とされてることをちょっと変えてみようって。そもそも、僕は家族というものに違和感を感じていて、介護や子育てに悩んだら、大家族で助け合うのがいちばんいいって言われがちなんです。昔みたいにそういう社会があればすごくいいと思いますよ。でも、いまは核家族化して、ファミリーといっても4人くらい。「もう社会が違うのに、昔の価値観を押しつけんなよ」って思ってしまって、その大家族神話を変えたいなと思いました。だから、「遠くの親戚より近くの他人」って掲げて、誰ひとり血はつながってないけど、一緒にやっていけてるんですよ。結局やってるのは、自分たちの子育てであり介護、自分たちの暮らしを生きやすいように、他人に頼ってるだけなんですけどね(笑)。僕は学校にあまり行ってないですけど、自分が成長した瞬間として覚えてるのは、本を読んだか、人と関わったかしかなかったです、いい人、悪い人含めて。だから、自分の子どもには年間200人の大人と会う環境をつくりたかった。それが、今は週に200人がうちに来るようになって。いろんな人と関わってたら、子どもは居心地いいだろうし、僕らにとっても、おじいちゃんおばあちゃんにとってもそうだよねって考えています。そんなに難しいことをやってるわけじゃなくて、高齢者になったら日常における登場人物は減っていくと思うんです。特に男の人は社会との関わりがなくなっていくので、その関わりを増やすというお手伝いだけをしています。それは、子どもも若い人もいろんな制約を抱えているなか、ひとりでできることってとても少ない。だから関わる人数を増やしていけば、いろんな実現可能性が上がるのかなって。
横堀 西川さんはどう見られましたでしょうか。
西川 面白いですね。僕は精神病院に15年いて、外来の血液透析、デイサービスでも実際に働いてましたけど、まあ、ケアする人間とケアされる人間しかいないところって、ロクなことが起きません。やっぱり強烈なのは精神病院。患者か医療者しかいない。そのなかで一生懸命に努力している医者も看護師もいるんですよ。けど、人の人生ってひとりの努力だとか、ある職種の努力でどないかできるものではまったくない。それに気づくのにすごく時間がかかりました。看護師というのは、アセスメントして、問題点を抽出して、それを解決するために介入するというのが今の基本なんです。要するに、相手は問題で、解決できるのはプロ、みたいになっているところで介護や医療の対象にされてしまうのが、どれくらい暴力的なことなのか。ケアの暴力性ってことを僕が発表すると、ボロクソに言われましたけどね。ケアって暴力じゃないという大前提があるわけです。
首藤さんの話で僕がいちばん気に入ったのは、「これが僕のいまの暮らしです、自分が暮らしやすいように生活してます」ってところ。自分の問題と地続きなんですね。自分も常に問題を抱えてるわけで、そういう出会い方ってお互いさまの関係ですから、相手は力を奪われることがないという気がします。認知症の人といろんな子どもがいてるというのは、臨床ケアのひとつとして結構前から取り上げられてるんですけど、あれはケアという目的をもってやってるんです。でも、首藤さんのところは、自分の子育てのためですから。だいたい今の社会では、まだ子どもがちゃんとしゃべらんうちから均質な集団の中に入れられるでしょ。育て親か先生という、役割がはっきりした大人が少数と、あとは自分と同い年の子とずっと一緒に過ごして、これが学校に行ってる間はずっと続きます。義務教育が終わっても、学力で輪切りにされてさらに均質的になっていく。会社に入ってもそうですよね、会社の利益のためにって目的が一緒なんですから。だから、社会的な役割をもって社会で生活をしようと思ったら、自分の周りには均質な人間ばかりがいることになる。それが効率いいから、今の社会はそうなってるわけですけど、そういう意味ではいつでも交換可能な部品なんですよね。周りの人間と同じだから、周りの人間と同じくらいの能力があるから、そこにいられる。で、ほんの少しでもそこからはずれると排除される。定年なんでまさにそうですよね。これがエイジング差別だって言い方もあるけど、なかなか本気に思っている人はいない。つまり、すごく均質的なところでしか今の社会では生きる場所がない。僕も学校に行ってないときには、世間に居場所ないなって思いました。自分の生きづらさ、生活しづらさと介護、子育て、そこを一緒にやってるところが、首藤さんの面白いところだと思いました。
首藤 まさに僕はそこだと思っています。自分の暮らしと仕事を一緒にすると、「それはあなたのエゴだ」って圧力もあるんだけど、じゃあ、もうエゴでいいやって。いまではエゴを社会化すると言っていて、自分の暮らしたいやり方をつきつめていけば、誰か同じように膝抱えて悩んでる人がいるから勝手に社会化するだろうなって。介護や医療の現場にはプロがいますけど、僕らがはっぴーの家をやるときに出したのは「一人のプロより百人に素人」ってことばで。だって、これから人口は減っていくんだから、素人百人といっしょにやるほうがいいんじゃないのって。
あと、むちゃくちゃしんどいときに、腑に落ちることばがひとつあれば人は生きられると思っていて。それで今、宗教の勉強をするようになったんですね。仏教って哲学やなって思うようになって。
西川 そういうことばに出会えるといいけど、やっぱりことばってだますからな(笑)。
首藤 正解じゃなくていいと思います。いろいろなことばがあっていいと思うんですよね。
西川 いまの首藤さんの話でもそうですけど、エゴを全面に出すってことは普通、社会が許さない。自分はたいしたことないけど、師匠を見る眼だけはあるなと思っていて、40過ぎて、大阪大学でもぐりをはじめて、大学中退してるのに大学院に入れてもらって、そこで出会った師匠は鷲田清一という人なんですけど。大阪大学の美学棟の西日の入る教室で、その言葉を聞いたときにはほんとに震えました。パスカルのことばで、強い者に従うのは必然だと。だから、強い者に従うことを正義と読み替えて、みたいなことをパスカルが書いてるわけです。いまの社会、ほとんどがそうかなって気もしますけど。そこで鷲田さんが言ったのは、「じゃあこれをひっくり返したらどうなるだろう」って。つまり、「弱い者に従うのが自由だ」って、静かな声で言われたんです。僕、そのときに、これは生きてきてよかったと思いましたね。自分のいままでの人生でも何もできないわけです。精神病院にいても「ありがとう」なんて一度も言われたことなくて、「おまえ、いつか殺したる」ってことは何度も言われましたけど。夜勤はじめて間もない頃、「おれ、きちがいやから」って詰め所に飛び込んでくる患者さんを前にして、自分では何もできない。「もう透析やめたい」って患者さんの話を聞いても、ベッドの横で立ってるしかない。亡くなっていく人を何度見送っても、できることなんて何もないわけです。そもそも、何かできるものとして考えるとダメだと思いますけど、それでもそこにいたってことは、君は自由なんだって鷲田さんに言われた気がして。だって、必然じゃないですか。精神病院でもたくさんいました、「こんなとこはイヤだ」ってやめていく人たち。そうやって出ていくことで精神病院の悪から目を背けることはできるけど、精神病院は存在し続けるんです。さまざまな問題からはずれてしまうのではなくて、無力でありながらその場に居続けて、下手をすると自分がいることが罪でありながらも居続けること。それは必然でもなんでもなくて、自分が選び取ったこと。
砂連尾さんでもそうですけど、より高く飛べるとか、より美しく踊れるというのではなくて、何度会っても覚えてもらえない、振り付けがまったく入らない、その彼女と踊るわけです。その砂連尾さんとミユキさんの姿には、だから自分をひっくり返すくらいの力があったんだと思います。だから、首藤さんの活動を聞いてね、もう一度あれですね、心を決めてやらなあかんなって気持ちになりました。
横堀 ありがとうございます。砂連尾さん、どうですか。西川さんがおっしゃった、弱い者に従うのは自由だって話。認知症の方といっしょにダンスをするというとき、砂連尾さんはどういう居かたをしようとされてるんでしょう。
砂連尾 どうなんでしょうね、たぶん、こういう居かただって言ってしまうと、そこに縛られてしまう不自由さを抱えてしまうので。このようにいたいっていうのは、たぶん全員違うと思うんですね。たとえば、はっぴーの家の話、とてもいいなと思うんですけど、でも、僕はここにいれるかなって思ったんです。それは悪い意味ではなくてですけど。すごくひとりでいたいときもあれば、めちゃくちゃ人としゃべりたいときもあって…。僕はいろんな人が生まれていくなかで、どこにも属さずにいたい感じ、ですかね。そういうことが可能かどうかわからないですけども。都合がいいですよね。都合がいいなって自分でも思います。
横堀 そういうものかもしれないですね。
西川 というか、弱さに従うって目の前の人を弱者として見るだけじゃなくて、自分の内なる弱さなんです。普通は隠しておきたいと思うようなこと。自分の弱さにもきちっと従うというのか…しょせん、できないことはできないんですよ。そうやって自分の弱さまでさらけ出したときに、周りの人たちも自分のヨロイを脱ぐ。お互いさまのところで、もう一度出会い直せる。普通は、同じだね、対等だねのお互いさまですけど、そうじゃなくて、お互いできないねってことの共通性があるときに、どれだけ一緒にいられるか。それがほんとはいちばん大事なことで。自分が行けば助けられると思うなら、行くのは当たり前のこと。けど、そうでないときにもいられるかどうか。自分の弱さをどれだけ出せるかどうか。これはね、簡単には出せないですよ。自分が崩れ去ってしまうかもしれないし、相手の攻撃をもろに受けるかもしれない。他人を信じられなかったら、自分の弱さって出せません。けど、ケアを受ける人は否応なしに自分の弱さをさらけ出さざるを得ない状況にあって。ケアする立場では、弱さを出さないことのほうが正しいと思われてる。でも、それって違うんじゃないかな。言ってみたら、ひとりになりたいときがあるという砂連尾さんが、相手に嫌がられたりもしながら、それでもやりましょうかってやってるところが、僕は案外好きでね。
横堀 ありがとうございます。今日は老いを巡る話をした後に、死を巡る話ができたらと思ってたんですけど、ちょっと時間がなくなってきました。触りだけになるかもしれませんが…。
首藤さんといろいろ話をする機会があって、そのときに首藤さんが仕事の醍醐味はお看取りの時間であるとおっしゃったんですね。それはなぜなのか。その後に、西川さんがブログで書かれていたテキストで「死んでゆくとは席を譲ること」「自分の死を苦しみとしてではなく、後に遺す人たちのために、ご馳走が用意されている席を譲ることとして考える」と書かれているのを読みました。そのあたりのことを少しでも話せたらと思います。まず首藤さんに。
首藤 そうですね。いままで生きる話ばかりしてきましたけど、僕もはじめ死に直面するまでは、怖いものだと思ってました。けど、日々いろんな人と関わっていると、このおばあちゃん、ここで死んでほしいなって思うようになるんです。それが第1フェイズ。その次に、たとえばそのおばあちゃんが死ぬときに、急に死ぬわけではなくて、弱っていく姿を見るし、「最後にあれを食べたい」っていう物を買ってきたりとか、すごく貴重なやり取りの時間があります。医療者の人は感じてはることだと思うけど、僕もやっていくなかで、そのやり甲斐を感じはじめました。そしたら、今度はこのおばあちゃんをどうやって死なせたあげたいかという発想になってきました。最期をどう迎えたいのかって見えてくると日々の関わり方も変わってくるんですよ。うちでも2年くらい前かな、ひとりのおじいちゃんの看取りをしました。まったく家族はいなくて、親族さんも死んだら勝手にやってくれって。生活保護の方やったんで、役場がやってる火葬場で焼かれて、式なども開かれない、すごい寂しい状態だったんです。そういえばこの方が創価学会の方やったんで、スマホで調べたら、お坊さんを呼ばなくてもいいとあったので、僕らでもできることあるんちゃうのって。地域の創価学会の人にも確認したら、「ぜひやったってほしい」と言われたので、僕の子どもらと4人、何もない畳だけの部屋でおじいちゃんの枕元にiPhoneを置いて、自分らで葬儀をやりました。YouTubeで「創価学会 葬儀」ってやれば、出てきたんですよ。めちゃクリエイティブなiPhoneの使い方をしたと思ってるんですけど(笑)。いろんな死に方、信仰があるけど、僕らの仕事はその最期にどう一緒におらせてもらうか。最期の1週間2週間って時間の感覚も違いますし、すごいやり甲斐がある。だから、この世の中、どう生きるかの話ばっかりになってしまってるけど、もっと死について、どう死ぬのかという問いの部分についてやっていきたいなと今、思っているところです。
横堀 砂連尾さんとも今日、ロビーでちょっと話してましたけど、この少子高齢化の時代に自分がどう死んでいくかの選択肢が限られている。死に方は変えられないんじゃないかって話もしましたよね。
砂連尾 つい最近、両親が亡くなって、母は、僕ら身内がいないなかでひとり死にたかったんだなと思う、そんな死に方をしました。僕は、母の最期を看取りたかったけど、それはたぶんエゴで。周りでそうやって関わりたいと思ってるだけで。その後、母と関係する人と会っていると、「お母さんは、たぶん理くんの前では死にたくなかったと思うわ」とかって言われて、そうだなって思ったりね。死というのはたぶん、自分が死ぬということだけではなくて、周りで関わっている人の思いも含めてあると思うんですけど…。自分は人に囲まれて死にたいのか、人じゃないものに囲まれて死にたいのか。それはまだわからないですけど、死というのもいろいろあるんだろうなとは思っていて。自分が死ぬときは選べないとも思うので。うちのおじいちゃんは、おばあちゃんの膝枕で死んで、こんないい死に方あるんだと思ったんですけど…。それを選べないことのダイナミズムもあるんだろうなと今は思ったりしています。
横堀 西川さん、どうなんでしょう。死に方というのは選択しているところもあるんでしょうか。
西川 どうなんでしょうね。僕が40代でいた血液透析の現場では、患者さんたちは週に3回は透析を受けて、それを続けないと亡くなります。そういう意味では、先にある死ではなくて、ほんとに背中に死を抱えている。僕たち、こうやって座っている間は、死を先のこととしてしゃべるんです。近いか遠いかは別にして、死は先にあることだと思っている。いや、死ってね、常に気づかないところから、背後からやってきますよ。死を前にした患者さんなり、お年寄りっていうのはそういうもんだと思います。自分もそうだろうなと思いますけど。当時は、40代だったのでターミナルケアということも真面目に考えていました。どんなケアをすればいいんだろうって。20年以上前の話ですから、まだ延命治療とか癌の病名告知もされてなかった頃です。それに対してどうするのか。死の準備教育だとか、死を常に意識することで自分の生をきちんとしたものにするだとか。そんなことを言ってましたけど、だんだん考えが変わってきました。看取りということは、何かをしてあげる、よい死を迎えさせてあげる、そういうことじゃなくて、亡くなっていく人から何を受け取るかなんです。人生ってたった1回しかない。その1度しかないことをしている人に、まだ死んだこともないような人間がね、ちょっと勉強したくらいで何ができるかって。何もできないですよ。そんなことを考えるくらいなら、目の前で死んでいく人から何を受け取るのか。看取りの場面にいたり、あるいは自分の大切な人が亡くなったという事実を知ったときに、「あれをしてあげられなかった」って自分の後悔をするんじゃなくて、相手が何を残していってくれたのかってことを考えるべきだろうって。だからといって、ターミナルケアが無駄なことだとは思ってませんけど。どんな人でもできることは、私がいま生きてるこの世のこの席を譲るということです。どんなに人のためを思っても、自分が生きてるかぎりは、この場所を譲ることはできません。どんな悪党であれ、この世を去るということは自分のいる場所を譲るということなんです。だから、譲られた場所を自分はどう生きるのか。いい死に方をしたいとか、そういう人意でなんとかなりそうだと思えるのは、生きている間の話で、死ぬってことは個人の能力を越えたもので。死ぬというのは、次の生まれてくるもの、今、生きてるものに対してこの世の席を譲ること。だから、生きてるということはすなわち、席を譲られたことなんだ。その譲られた先を次の者に譲るまでどう生きるか、そこがいちばん大事なんじゃないかな。人間の哲学や思想を越えたところに、誕生や死というものはあると思う。って、ここで思考停止すると哲学じゃないんでね(笑)、まだ考え続けてますけども。
横堀 今回のために事前にいただいた相談がいくつかあるので、ここから残り時間、ひとつふたつほどお答えいただいてもいいでしょうか。「両親のことです。老いれば老いるほどに頑固にどんどんなっていきます。上手なつきあい方はありますか」。首藤さん、どうでしょう。
首藤 さっきの話とつながるんですけど、僕らの世代で死ぬってなったら、たぶん死に方は選べないですよね。突然死だったりで。でも、おじいちゃんおばあちゃんは、ある程度、選べる場所にいるのかなと思っていて、自分の死について考えるチャンスはあるのに、なんとなく死んでいく人が多いなと思います。それが自分の両親だったとしても、どう死にたいのかって本人の意志を聞いてあげたくて。いまの質問に対しての答えとは違うかもですけど、どう死にたいのかってもっと社会的に聞けるようになったら、どう生きたいのかにつながるのかなって。もっと聞くとか、表に出していくことでちょっと変わってくるものがあるのかなと思います。
西川 年をとって頑固になる人もいれば、かわいくなる人もいる、ケチンボになる人もいるし、様々ですけど、相手が変わったんなら、自分も変わらなければねと思います。あんなにものわかりのいい親だったのにって、いつまでも相手が変わらないもののように思っているのは、こちらの勝手ですから。生きているとそうやって変わっていく。相手が自分の思うようなままではいてくれないし、自分だってきっと変わっていくんです。つきあうだけが共にいる居かたじゃないんで、とりあえずきれいに別れてみるとか。親であっても、自分の幼い頃に愛してきたときのままではいつまでもいられないって覚悟しないといけないんじゃないでしょうか。
横堀 ありがとうございます。また別の方からの質問、「死ぬことが怖くて怖くて寝つけないことがあります。どうしたらその怖さを和らげることができるでしょう」。
砂連尾 体験したことないんでね、怖いでしょうね。僕も怖いと思う。ですけど、舞台をやっていると必ずはじめと終わりをつくらないといけないことを、舞台人は多く体験していると思います。練習をやっていても、終わりとはじまりをつくらなけれいけない。その終わるまでの時間をどう過ごして、どう存在するのかってことを、舞台というフィクショナルな場所でやりながら、練習してるのかなあと思います。
西川 砂連尾さん、別れのダンスってやってたじゃないですか。あれでいいんじゃないの。
砂連尾 別れのダンスは、東日本大震災の被災地を訪ねるなかでインスピレーションを得たもので、急に関係のあった人がいなくなってしまう、その瞬間みたいなものが多く起きた場所と時間があったわけです。最後までどう掴んでいたいかみたいなことがあって、手を掴んで…。
西川 離れたときに一気にウワッてなるんです。別れるまでの時間を大切にしようとかってそんな考えが先にあって、計画的に味わえるものじゃない。ずっとつながっていて離れたくないとかって言っても、その手が離れたときに一気にやってくる。映画でもそうです。最後のジ・エンドが流れてくるまでは、場面を追いかけるのに必死で、追いかけることに意味があるかのように思うけど、ほんとに終わったときに。それまでのことがいきなりくる。それは自分の努力とかじゃなくて。大切な人を亡くしたときに、どれだけ大切な人だったかということは、いきなりくる。死を自分たちの様々なものをゼロにする不条理なものだと考えると、恐怖の対象になりますけど、死には、それまでいたことの意味が一挙にわかるという側面もあると思います。僕が言ってることが正しいかどうかわかりませんが、そんな風に考えなおすこともできる。いや、考えるんじゃなくて、やっぱり死ななきゃダメです。死ななきゃ生きてきた甲斐がない。という気がしますけど。
首藤 相談者の方は不安で寝れないですね(笑)。
横堀 私も1年半前にクモ膜下出血をやりましたけど、びっくりしました。死が隣りにあったんやと思って。ずっと先にあるんやと思ってました。
西川 哲学は死の練習だってプラトンが言ったらしいですけど、ほんとかなって思う。なかなか練習は練習でね。
首藤 僕、今の仕事をしていたら日常的に死を見すぎて、プライベートでも大切な人を亡くしたりとかがあって、死のときに気づくことがたくさんあるな、すごくいただいてるなって思うようになりました。そして僕自身は、常に明日死ぬって思うようになりました。そしたら、今までやってた余計なことを選択しなくなりました。ときどき、自分が死ぬってことを忘れるときがあって、それは自分がブレてるんですよ。だから、そうや俺、明日死ぬなって定期的に思うようにしてますね。
西川 若い人はね、明日死ぬかもしれないって言うんだけど、明日じゃない、今日死ぬんです。明日って人間にとってリアルじゃない。常に今しか生きてないんで、死ぬというのは今にしか訪れない。先にあるものとしての死というイメージが強烈なんでね…ってこんなことを言っていくと、だんだん時間とはどういうものなのかって哲学議論に入っていっちゃうので、それは趣味でやりましょうという感じですね(笑)。
横堀 ありがとうございます。時間をちょっと過ぎてしましましたが、この回はここで終了させていただきたいと思います。砂連尾さん、西川さん、首藤さん、どうもありがとうございました。
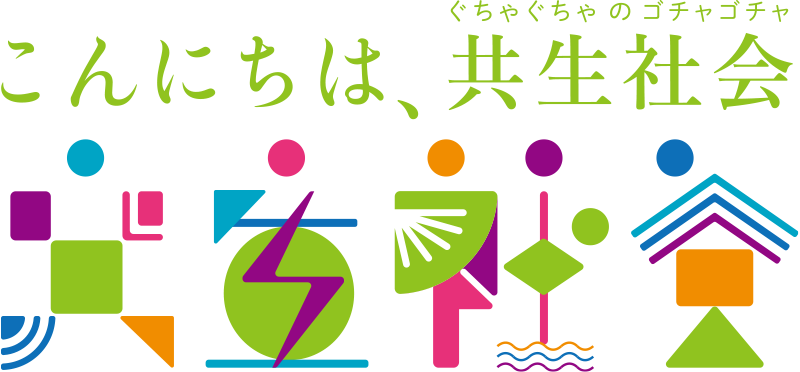
こんにちは、共生社会とは
障がいの有無、経済環境や家庭環境、国籍、性別など、一人一人の差異を優劣という物差しではなく独自性ととらえ、幾重にも循環していく関係性を生み出すことを目的としたプロジェクトです。2019年に神戸市長田区で劇場を運営するNPO法人DANCE BOXにより始動しました。舞台芸術を軸に、誰もが豊かに暮らし、芸術文化を楽しみ、表現に向かい合うことのできる社会をめざす、多角的な芸術文化創造活動です。
